本題
先日、大学4年生から研究計画書についてのコンサル依頼を受けました。
最近の傾向として、大学生の段階から将来の税理士資格取得に向けての相談を受けることが、2年前に比べて増えてきているように感じます。
その要因として考えられるのは、社会保障や増税など将来への不安要素が高まる中、税理士という資格を取得して手に職を付けたいと考える傾向が強くなってきたのだと感じました。
最近の私の研究計画書のテーマとしてお伝えする内容として、タインズから抽出するケースが多いです。
というのも、タインズであれば、地裁から最高裁まで一気通貫した判例資料を集めることができ、さらに最新の判例を収集することができるため、より合格に近づくための資料収集をすることができるからです。
ただ、タインズは基本的に税理士専用のコンテンツであるため、大学生はそもそも使えません。
会計事務所で働いている場合は、所長にお願いしたり、所長が元々知り合いだったりする場合があるので、タインズから物理的に資料収集することが可能で、現に私が大学院生の時は周りの社会人の方はタインズから資料収集をされていました。
なので、大学生については、タインズを利用していると、どうやって手に入れたのかという教授の疑念を生んでしまうことになるので、大学生の大学院受験についてはタインズを利用すべきでないという結論になるわけです。
そうなってくると、収集できる材料は限られてきます。
そもそも税法の雑誌というのは多くありません。
法学の中でも税法というのは特殊な分野です。
税法の雑誌で有名どころでいうと租税判例百選になります。
なので、多くの大学生は租税判例百選からテーマを選ぶことになります。
ただ、この租税判例百選、現在、第7版ですが、第6版から変更になった判例は17つほどしかありません。
税法の判例というのも毎年多くはないので、新しい事例が物理的に発生しません。
だから、租税判例百選から選ぶテーマというのは、みんな偏りガチになります。
その中から、大学生でも扱えるキラリと光るようなテーマを選ぶようなお手伝いを私のコンサルではやっています。
これ以上は、有料でコンサルを受講していただいた受験生がいますので、気になる方は、すぽっと顧問をご利用ください。
宣伝かいっ!!
本ブログ記事の無断転載はおやめください
息子&娘(7歳11ヶ月&3歳11ヶ月)の成長日記
ガリガリくんのあたり棒を持って、夜のコンビニへ息子と一緒に行きました。
しかし、レジをしているのは留学生と思われる外国人の方が2人、チェンジとか言って伝えようとしましたが、ガリガリくんのあたり棒のシステムは伝わらず、コード決済することにしました。
文化の違いの好例じゃないかと思いました。
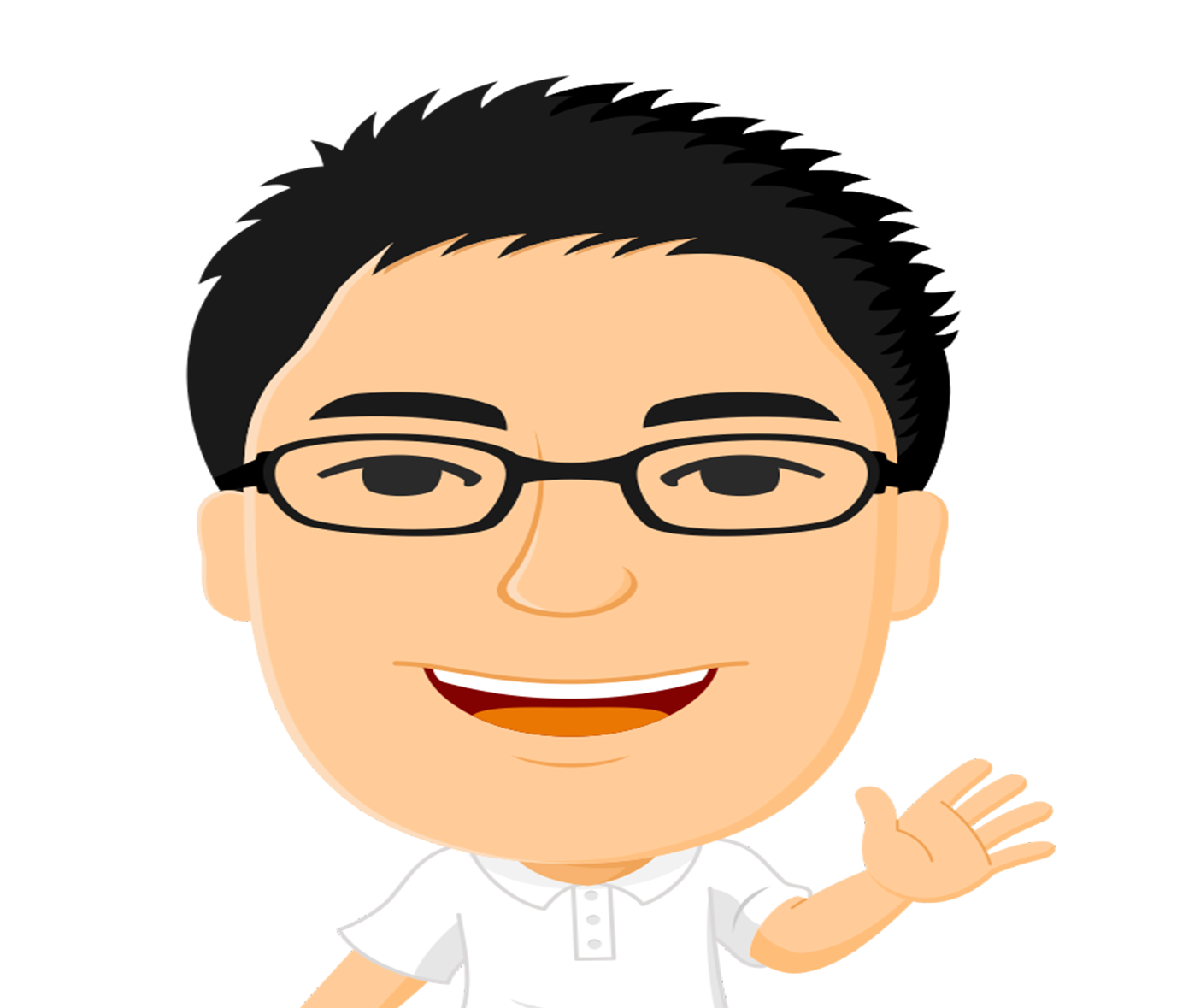
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。

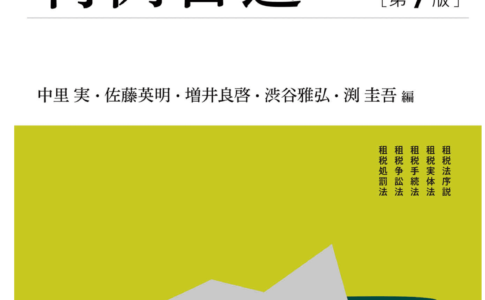









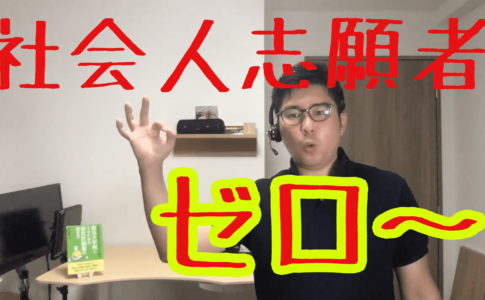







相続税申告はこちら