本題
税理士になると、会報誌の近畿税理士界が毎月送られてきます。
そこには、その月に近畿税理士会に登録した税理士や、事務所移転などで退会した税理士が載っていたりします。
税理士になる前は、税理士界という会報誌があること自体知りませんでした。
この近畿税理士界ですが、コラム記事であったり会員である税理士先生の研究などの発表があったりします。
その中で、第736号で草津支部の原浩崇先生が書かれた研究レポートがあったので、少し紹介したいと思います。
内容は、民法と相続税法における取り扱いの違いについてでした。
非常に興味深いタイトルです。
養子の数について
例えば、養子の数について、民法では、養子の数に制限がありません。
そして、相続税法では養子の数に制限はありませんが、基礎控除(3,000万円+法定相続人✖︎600万円)で認められる養子の数の数が決まっています。
①実子のいる場合は1人まで②実子がいない場合は2人まで③特別養子縁組による養子は実子みなされ、人数制限の対象外となっている。これは、何人と養子縁組したかによって、控除額が極端に変わるのは課税の公平性に反するからである。
相続放棄について
次に相続放棄について、民法では、相続放棄した者は初めから相続人ではなかったことになる。
そして、相続税法では基礎控除に算定する法定相続人の人数を計算する際は「相続放棄がなかった」ものとして人数に含めて計算する。
①誰かが相続放棄をしたか否かによって、控除額が変わるのは課税の公平性に反するし、②もし相続放棄によって法定相続人の数が変わることになれば、相続放棄によって法定相続人の数を調整することにより課税の公平を欠くことになるからである。
その他
このブログでは、割愛させていただきますが、上記の他に以下の項目について民法と相続税法においての違いについて考察されていました。
- 相続財産
- 財産評価時
- 特別受益
- 期間制限
期間制限について
期間制限については、何の?となりそうなので、補足をしておくと、これは、特別受益や遺留分の算定における期間制限について、元々、期間の制限がなかったものを特別受益については、令和5年4月1日以降に生じた相続につき、相続開始から10年経過した後に行う遺産分割については、特別受益と寄与分の主張ができないこととなった。
令和元年7月1日以降に生じた相続についての「具体的遺留分」の算定においての10年以内の期間が設けられた改正などに触れ、相続税法では、暦年贈与が相続税の計算上、規定の年分、相続財産に含めて相続税を計算されることと対比して、相続税法が「課税上の公平性の確保」「課税逃れの防止」を目的としていることを確認した内容となっていました。
おわりに
税法大学院における研究計画書で、相続税のテーマを書く際は、民法が必ず影響を与えます。
民法と相続税法の目的の違いから両者の規定を比較するのも面白いと思いますし、この違いが原因で発生した判例などを読む際には、目的の違いを意識することで、より深みのある研究計画書を書いていくことができると思います。
研究計画書は、教授に向けた小説ですからね。
本ブログ記事の無断転載はおやめください
息子&娘(8歳0ヶ月&4歳0ヶ月)の成長日記
京セラドームで巨人戦が開催されているのを知って息子を誘ってみると、今からチケット取れるの?と大人な質問が返ってきました。
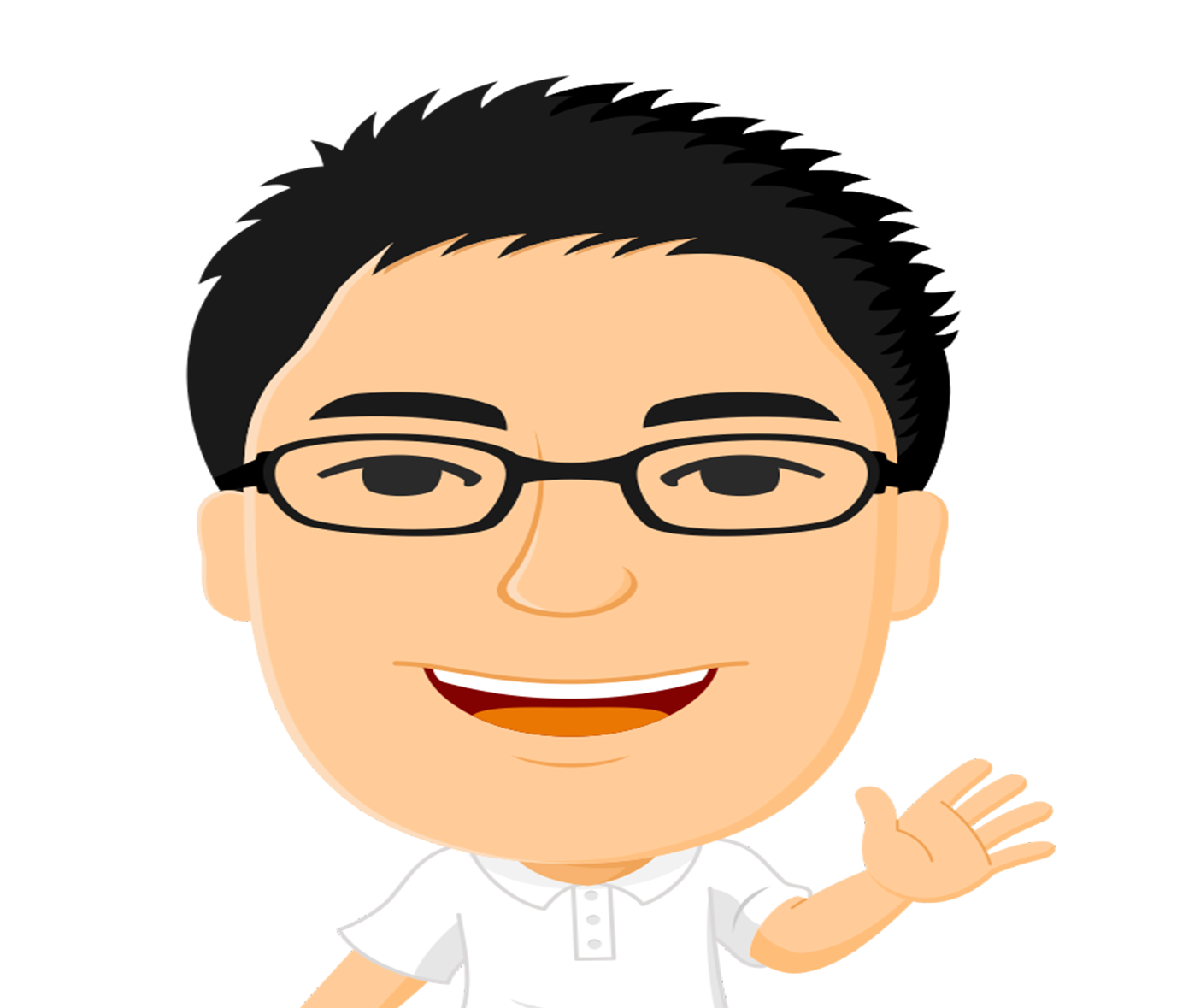
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。





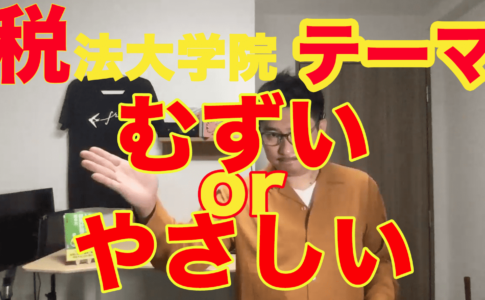
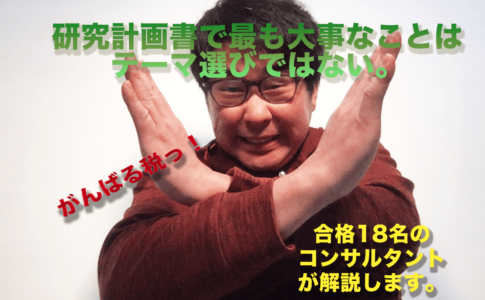
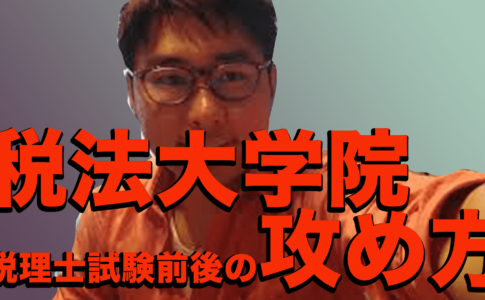


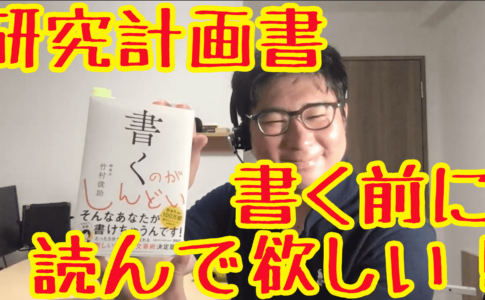







相続税申告はこちら